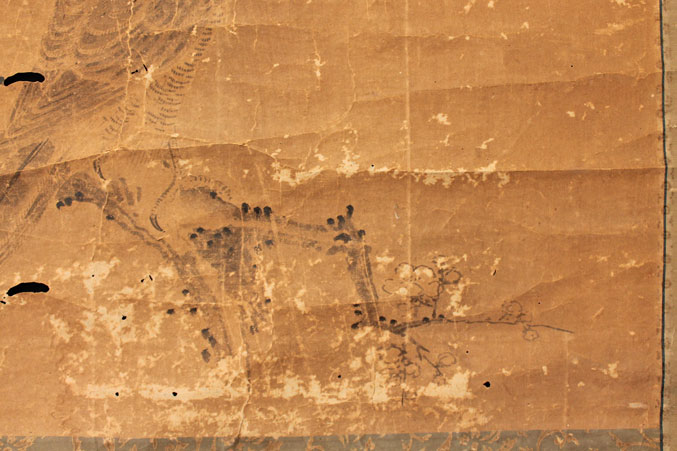掛け軸の保存|表具師(表装技能士)錦司堂
掛け軸の保存と取り扱い
掛け軸の長期の掛け放しは、湾曲や光による退色の影響を受けますので禁物です。よって、展示後は桐箱に収納が理想です。
掛け軸の取り扱い方
・新装の軸は1日から2日位掛けましたら、巻いてください。当分は掛けたり、巻いたりするのが良いでしょう。
・冷房の効きすぎた部屋や、風通しが烈しい所、また湿気の多い所に掛けられることはご遠慮ください。
・連日掛けたままになさらず、時々巻いておさめてください。
・風帯は左右に折り重ねて巻いてください。
掛け軸が反り等の湾曲が生じた場合
近年は家の気密性も良く、エアコン・石油ストーブや加湿器等も普及して、急激な温湿度の変化が生じやすくなっています。
それにより掛け軸に変形が生じる条件が増加しました。もしそのような状態になったら、直ぐに巻いて収めてください。
ある程度回復しますが、それでも湾曲が大きい場合は応急処置を行い、場合により表装店で治すことになります。
掛け放しにされる場合
諸事情により、掛け軸を掛けたままにされる場合があります。祭壇の奥に掛けられて、頻繁に取り外しが困難なこと。また、掛け放して使用すること等の場合は、以下の対処を行います。
化学糊の使用
従来からの掛け軸は、自然の原料を加工した糊を使用しています。湿度には比較的弱く、糊成分が枯れて馴染むまでは時間がかかります。将来の安全な再修理を優先するため、文化財の掛け軸には全工程で使用されます。上記の糊に代わり、全て化学糊で掛け軸に仕立てることで、温湿度の影響を受けにくいとされています。将来の再修復も可能ですが、通常は寺宝級の高級掛け軸には控えます。
額装にする
掛け軸の形に、周囲に額枠がつきます。額形式ですので、飛び出た紐や軸はありません。
【長所】掛け放しでの湾曲は生じませんし、取り外しも容易です。
【短所】巻いて保存することができませんので、色褪せや劣化が掛け軸より早く生じます。その場合は、アクリルガラスを取り付ける方式にして、緩和します。
桐箱で保存
掛け軸は通常桐箱に入れて保存します。桐箱製造は外部業者に委託します。
【並品】通常は並品での保存となります。
外国産の桐を使用して、蓋の部分になるべく木目が良い板を使用します。
予め一定の間隔で作られている桐箱があります。そちらに掛け軸の仕上がり寸法に合わせて、詰めをして調整します。
身と蓋が合う方向があります。方向が異なりますと、身と蓋に多少の段差が生じます。片合と言われます。但し、保存に影響はありません。

【上品】対象として寺宝級等の掛け軸になります。
蓋だけではなく、側面にも木目が良い板を使用します。
身と蓋が、方向に関係なくピッタリと閉まり両合と言われます。
掛け軸のヨコ寸法に合わせて、特別に作ります。また箱書きに適しています。

【二重箱】桐箱の外側に塗り箱が加わります。
保存箱は二重になります。
有名にな日本画の作品によく見られました。
太巻き棒で太く巻いて保存
横折れによる損傷が多く見られます。それは掛け軸の構造上巻いて保存することで、修理後も遠い将来に再発生する可能性があります。桐材芯棒で太く巻くことで、横折れを緩和します。

桐製の開閉する円筒を、軸棒に挟み込みます。
太巻きは、掛け軸の巾や軸棒の大きさに合わせて製造しています。

掛け軸を巻いた時の直径が太くなります。

掛け軸を巻いた、太巻き芯棒と桐箱。
通常の桐箱より、幅が広くなります。

太巻き直径を調節することもできます。
古い箱に文字記録がある場合
蓋の部分に書かれてる場合が多く、掛け軸修理後も一緒に保存することになります。
文字部分の板のみを保存
修理前に保存していた箱自体が古く破損していることがあります。また掛け軸修理後に、再び収納することができない場合があります。また文字記録がある場合は、掛け軸と一緒に保存しなければなりませんので、箱の処分はできません。 解体前の箱
解体前の箱
掛け軸を修理した後に保存する箱
記録している部分が、蓋のみでしたので費用的には一番かかりません。通常はこちらの方法が多いです。箱の底に、蓋部分を敷いて保存します。修理した後の掛け軸は、その上に収納します。また蓋部分に、部材を付け足して箱を製作する場合もありますが、より費用がかかります。 旧蓋以外は、新調
旧蓋以外は、新調
太巻き芯棒で保存することに変更した場合は、今までの箱に入らなくなります。
その場合は、蓋に書かれた箱書の部分を切り取って、部材を付け足して新しく桐箱を製造します。
掛け軸の掛け方・しまい方

和室の中には、一段高い神聖な場所があります。 それは床の間と呼ばれています。
その季節に関する画や、芸術性の高い書等の掛軸が掛けられます。
現代のモダンな建築設計でも和室は残されつつあります。
掛け軸の掛け方
❶ 桐箱から掛軸を取り出します。
❷ (風帯がある場合) 
畳の上で上部分まで広げて、横に折り畳んであった風帯を下におろします。
❸ 矢筈で掛軸に引っ掛けます。
片方の手では軸を下から支えます。
❹ 軸釘に掛けます。
片方の手は、軸を下から支えた状態です。
❺ 矢筈を外します。
両端の軸首を持ってゆっくりと下します。
掛け軸のしまい方
❶ 両端を持って掛軸の上部まで巻き上げます。
❷ 矢筈で掛け緒を引っ掛けて、釘から外します。また片手で掛軸の下から支えておきます。
❸ 畳の上に置き、風帯を左右に折り畳んで巻きます。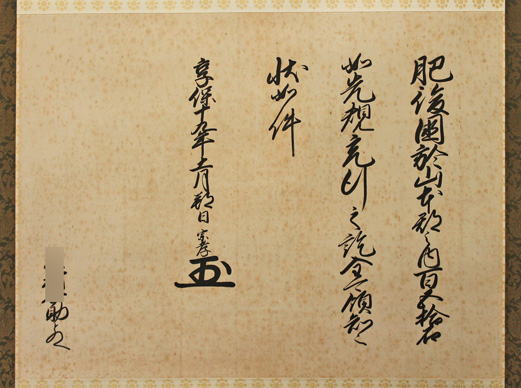
➍ 風帯を左右に折り畳んで紙を敷きます。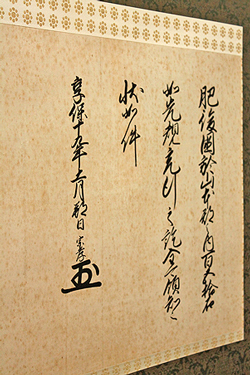
風帯を左右に畳んだ状態。
その下に紐下紙があれば、敷きます。
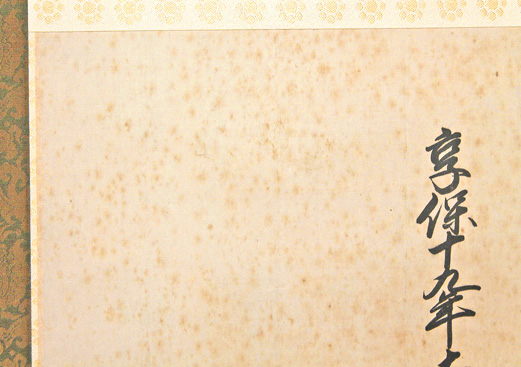
巻紙
巻紙を掛け軸に沿って巻きます。
❺ 紐を巻きます。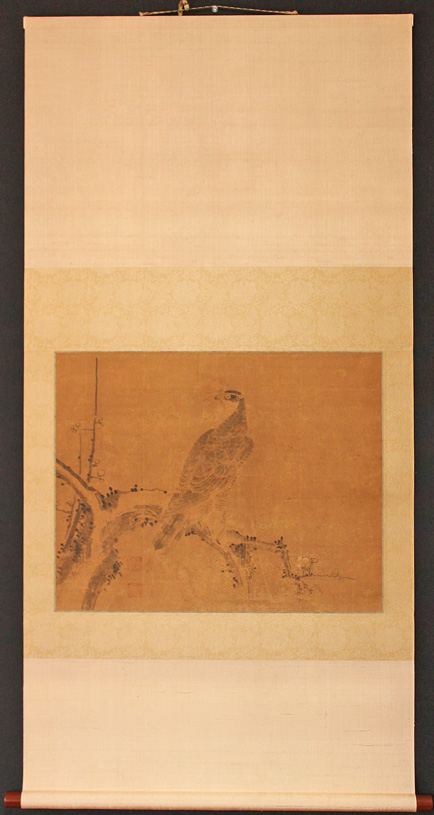
巻き紙の上に紐を巻きます。下方面に巻いていきます。
他に上に巻く方法もあります。
❻ 3回目で掛け紐を下から上へ潜らせます。
❼ 紐の端を折って2重にして、左側の紐下に通します。
❽ 八の字にします。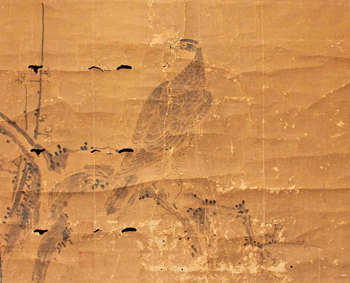
左側の紐は2重で、右側は1重です。
右紐を引くと解けます。
❾箱に入れます。軸枕の広い方を上にします。